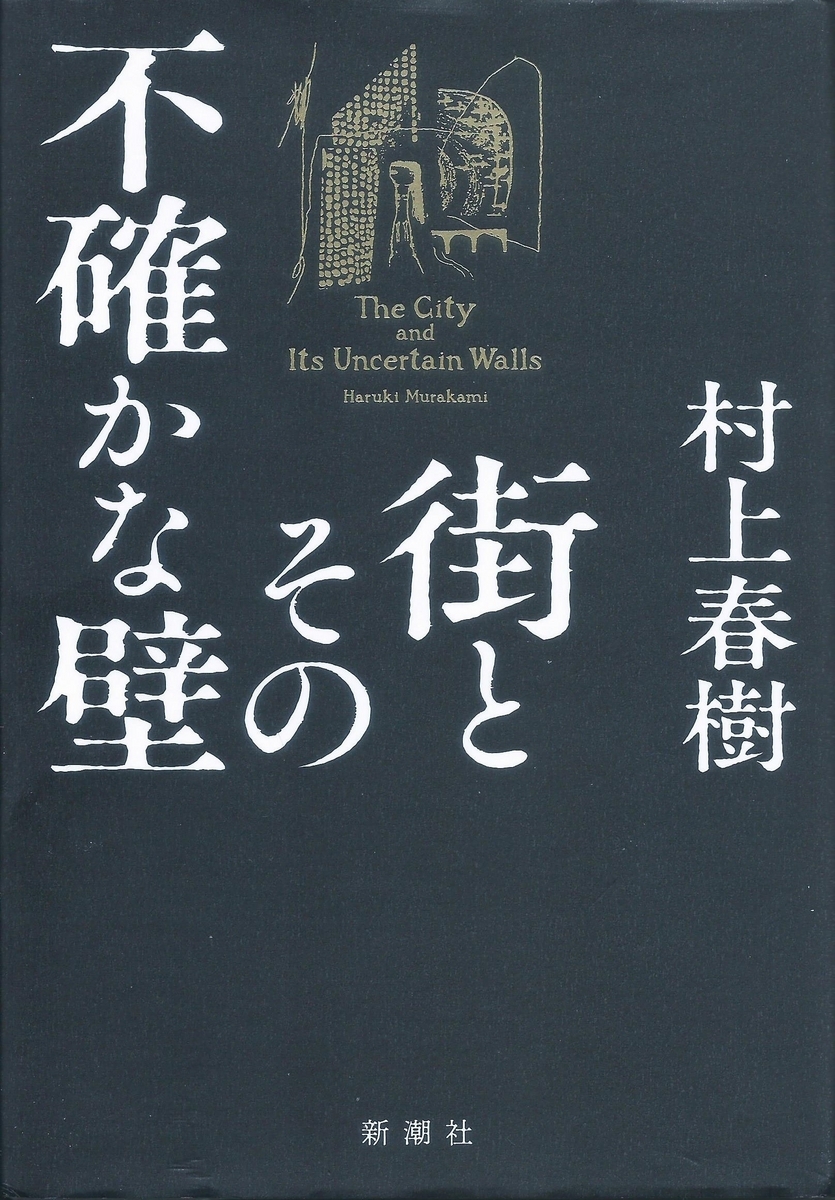
多少のネタバレ有り! 読みながら幸せな気持ちになったり、悲しくなり涙をながしたり…
昨年(2023年)の4月13日に発売された本作を私は発売日に購入した。
だが、その時は他に読まなければならない本があって、すぐには読まなかったはずである。
読み始めるもなぜか、116ページで読みとめてしまった(それがなぜなのかはいまだにわからない)。
その後、読もうと思いながら、何度も何度も寝室とリビングの間を往復したこの小説は、一昨日になり、ふと続きが読みたくなった。購入してから10ヶ月以上経っている。
ふと読みたくなったきっかけはあった。
それは、雪が降っている午後にワーグナーの『ニーベルングの指環』から序夜「ラインの黄金」のとある演奏を聴いていたときに、唐突にこの『街とその不確かな壁』を手に取り、しおり(わたしは単行本や新潮文庫を読むときには備え付けられているスピンは使わない)が挟んであるページを開いた。すると文字が目から脳に伝えられ、しっかりとした映像となって人物たちが話し始めたのだ。
そのときに聴いていた『ニーベルングの指環』が有名なショルティ指揮やカラヤン指揮の録音であったらこうはならなかったと思う。この時に聴いたのはルドルフ・モラルトという指揮者が1948年から49年にかけてラジオ放送のために録音したものであった。非常にマイナーな録音であるが、初夏の朝にカッコウの泣き声を聞くように、変に力が入っておらず、自然体な演奏・歌唱で、とても耳心地がよかった。
通常、私は音楽を聴きながら読書をしない。内容が頭に入ってこないからだ。あと、これは皆さまにもあるかもしれないが、定期的に本が読めなくなる期間が来たりする。1、2週間……長ければ1ヵ月ほど。また、昔はよく電車の中で読書をしていたものだが、ここ数年は一切できない。電車の中で本を開いたらすぐに睡魔が襲ってきてしまう。なぜだろう? まったく読書とは不思議なものだ。
そういうことで「ラインの黄金」を聴きながら小説をはじめから読みなおし、ドンナーが金づちを打ち付けてヴァルハラに虹の橋が架かり、神々が渡り始めて最後の和音が響いた時に本を閉じた。
翌日の第1夜「ワルキューレ」もすんなりと小説の物語とシンクロをし(不思議なことに小説の悲しいシーンでの音楽は悲しい場面の音楽、愉快なシーンでは愉快な場面の音楽だったりするのだ)、第2夜「ジークフリート」の第2幕を聴き終えて、この日が終わった。
本日は「ジークフリート」の第3幕からスタートした。さすらい人としてジークフリートの前に出てくるヴォータン(神々の長であり、ジークフリートの祖父にあたる)が退場するときに小説の中で重要なキャラクターも退場をした。わたしはここで本当に悲しくなって泣いてしまった。涙がポロポロとこぼれた。その後、スピーカーからはジークフリート牧歌のメロディが聴こえてきた。この、老夫婦が最後のダンスを踊っているかのような暖かなメロディがこんなにも心にしみたのは初めてだった。
最終夜「神々の黄昏」に入ると、小説の物語も佳境に入っていた。小説の中の「僕」とコーヒーショップの「彼女」がマルゲリータのピザを食べて、二階に上がりささやかな愛を語り合っているときに第1幕が終わった。
第1部が177ページ、第2部が413ページといういびつなこの小説は、たった56ページしかない第3部に入る。スピーカーからアルベリヒとハーゲンとの陰謀が聴こえている。この第3部では表の世界にいる「僕」とコーヒーショップの「彼女」が出てこずに終わると知ると、急にまた切なくなってきてしまった。
購入して10ヶ月放置していた『街とその不確かな壁』は、結局は3日間、通算約13時間ほどで読めてしまった。
読めない期間はなにかしらの意味があったのかもしれない(それがなにであるのかはわからないのだが)。しかし、モラルト指揮のワーグナーの音楽は大切なきっかけとなったのは確かであり、そして、不思議なことに終始、小説の内容と音楽は連獅子の髪を振り回す親子のようにシンクロをしていた。
読み終わり、このブログのために久しぶりに本にカバーを戻してスキャンし(このブログでは電子書籍以外は実際に読んだ本の書影をスキャンして使っている)、本記事を書いているが、あらためて村上春樹さんは日本近現代文学の正当な後継者であると確信をした。確信をした部分は主人公が受動的な点である。
村上春樹文学はアメリカ文学……レイモンド・チャンドラーやカート・ヴォネガットJr. の影響が濃いと言われている。わたしはチャンドラーは読んだことがなく、ヴォネガットJr. は『タイタンの妖女』しか読んでいないので、そこら辺はよくわからないのであるが、みずから動かない主人公・周りの影響によって左右される主人公は近現代の日本文学の大きな特徴の一つだと思っている。わたしは逆に能動的な主人公の小説は苦手なタイプだ。
『街とその不確かな壁』を遅くはなったが、無事に読めたことにこの上ない幸福感と充実感が得られた。
時代と自己を行ったり来たりして読者にとって多大に想像力を要求する小説であるが、ぜひ読んでもらいたい一冊である。
(新潮社 2023年 奥付には第1刷とは書かれていないが第1刷だと思う)
