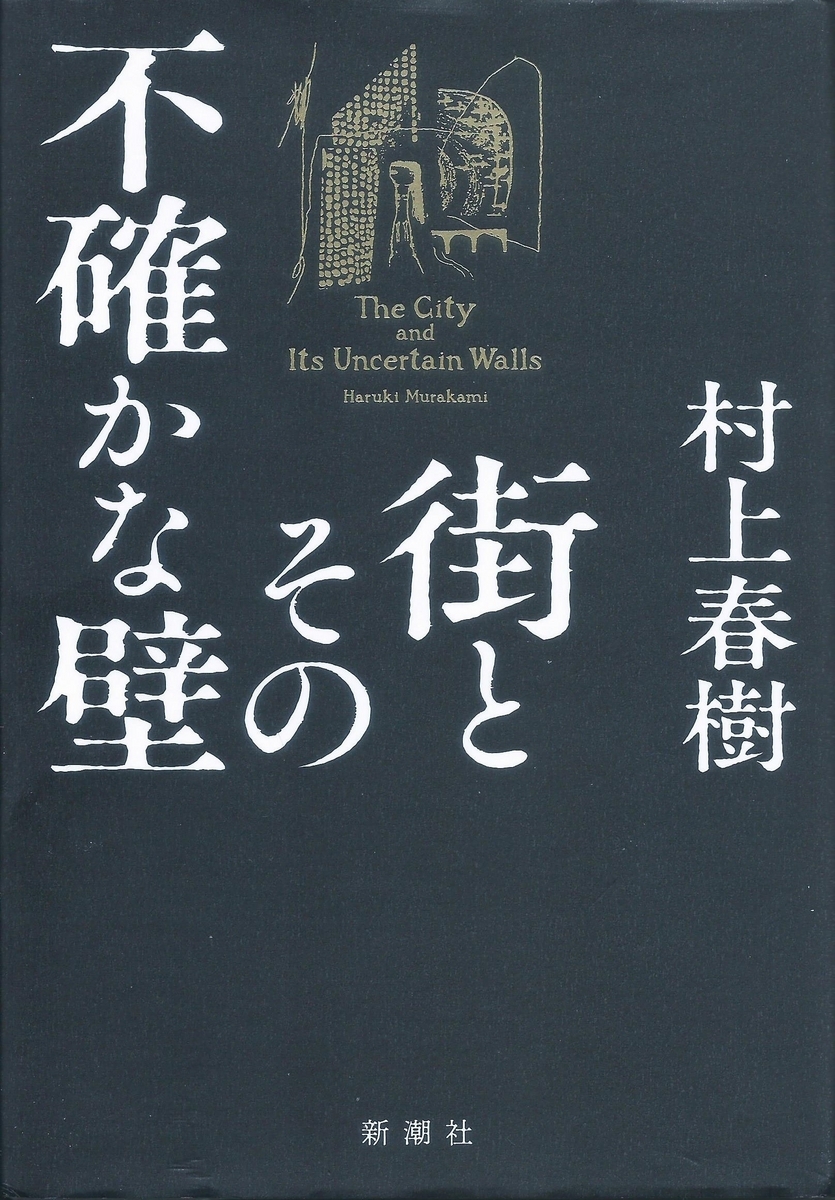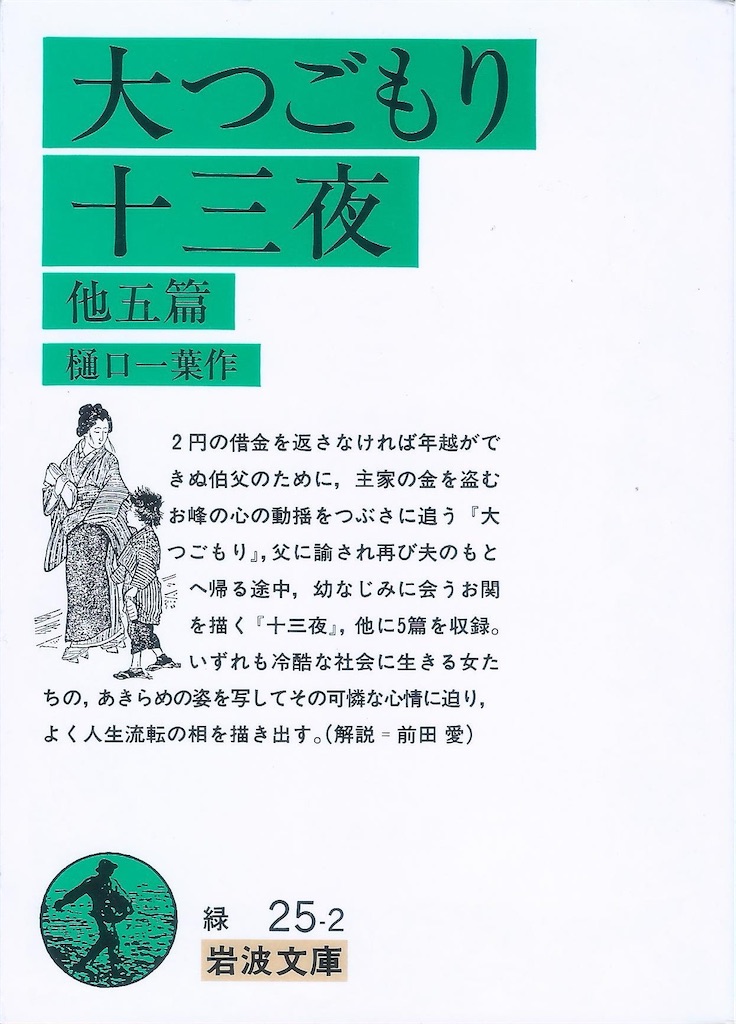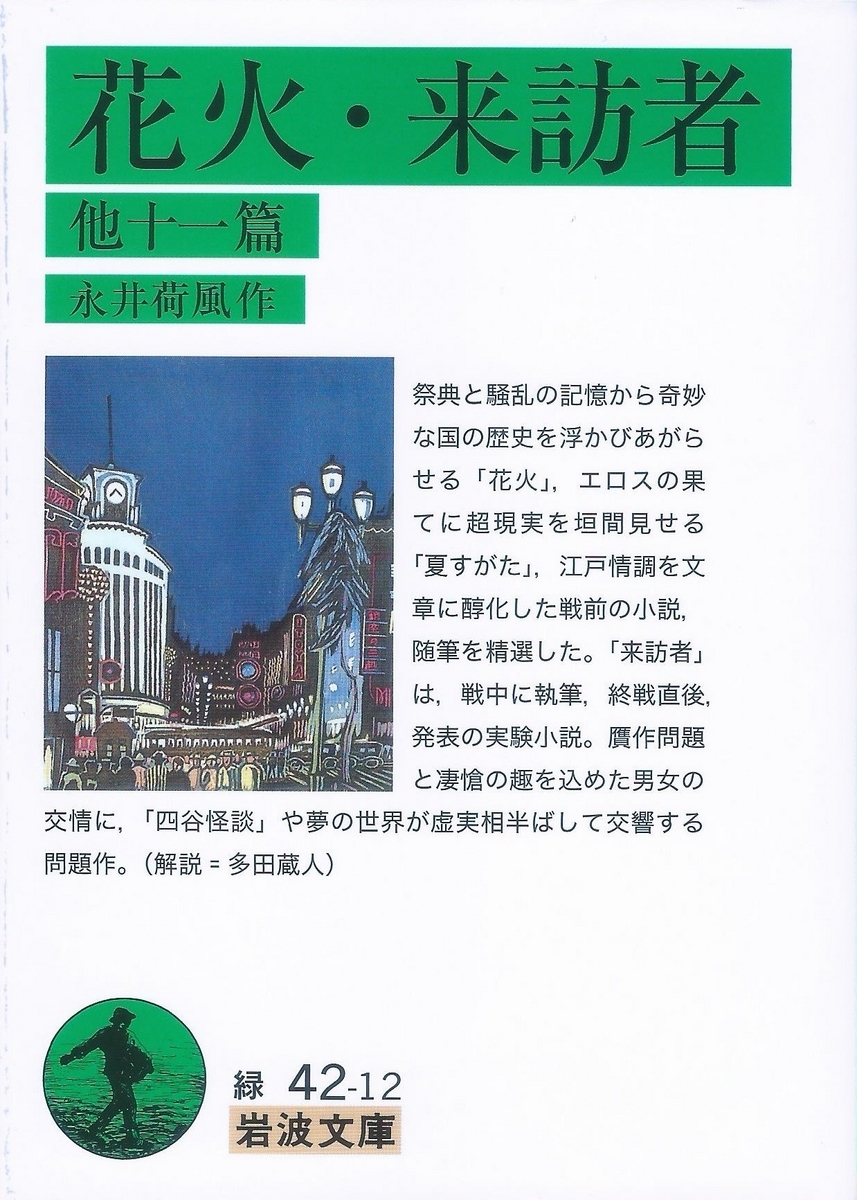多少のネタバレあり。鬼才・天才・変態・モンスター・狂人と言われるソローキンの17作の短編集。ただのエログロだと思って読むべからず。あなたの深層心理が臓物の中から鷲掴みでひねり出される。
本作はロシアの作家ウラジーミル・ソローキン(現在はドイツ在住)が1992年に発表した短編集である。ちなみに『愛』は1作目に収められている作品名で、原著の直訳は『作品集』である。
本書に「可能性」という短編がある。
とても短い話で、短編というよりも掌編と呼んだ方が良いかもしれない。
あらすじは(おそらく)老境に入った男が「人にはなにができるだろうか?」ソローキン著 亀山訳 『新装版 愛』, 2023, p. 56 と問う。
「湿った壁に手で触れることか? それとも、田舎者の白っぽい顔をした老婆に会うという望みを抱きながら、汚れた黒い階段を上ること?〈中略)冷蔵庫から肉を取りだすこと?」ソローキン著 亀山訳 『新装版 愛』, 2023, p. 56-57 などとあらゆることを振り返りながら、人生の斜陽に差し掛かっている自らの可能性を問う。
ちなみに言っておくが、この短編集『愛』には必要最低限の説明しか書かれていない。よって「可能性」の語り手が上に記したように老境に入った男かどうかはわからない。あくまでも私が行間から感じたシチュエーションである。
この男は「人にはなにができるだろうか?」を執拗に自らに問う。
「煙だらけの部屋を歩き回ること? 古い食器棚のガラスを泣きながら割ること? 小便をかけるか、たんにおしっこする……。だが、できることは、小便をたれること、ないしはたんにおしっこする。おしっこする。おしっこするのはきもちいい。おしっこするのはいい。おしっこするのはいい。あまったるくおしっこする。ながいことおしっこする。〈後略〉」ソローキン著 亀山訳 『新装版 愛』, 2023, p. 58
このさきはずっと「おしっこ」のことが書かれているのだが、ソローキンは決して面白半分で「おしっこ」のことなんて書かない。「人にはなにができるのだろうか?」という設問に対しての最終的な帰結が「おしっこ」なのだ。
「弔辞」という短編がある。ニコライ・エルミーロフの棺桶が音楽隊の葬送行進曲によって墓地に運ばれていく。ちなみに棺桶の中には遺体は入っていない。墓穴に棺桶が到着し、家族や友人がお別れをする。墓掘り人夫たちが一斉に棺桶にむかって射撃をする。ここで初めてニコライ・エルミーロフは遺体となる。棺桶に土が掛けられて、故人の家で通夜が行われる。友人たちが弔辞を読む。セリョージャという友人はニコライのことを偉人と称える。彼がなぜに偉人であったかを参列している人々に話す。セリョージャは生まれつきペニスが未発達で、勃起しても9センチしかない。そのために妻と離婚危機を迎えている。そんな悩みをニコライは見抜き、セリョージャから殺人を犯し、肛門性交をすれば万事大丈夫と勇気づけられ、その2つを果たしたセリョージャはすべてが丸く収まった。ニコライは偉大である。と話した後、むき出しになった勃起した股間を一堂にさらす。この勃起したペニスこそがニコライの偉大性を伝えている。
「寄り道」という短編ではこのような文章がある。
「ゲオルギー・イワーノヴィチは大声で呻きだした。血の気のうせたかれの唇はだらしなく開かれ、目はかすかに開いていた。彼の膝をよけながら、フォーミンはデスクを一回りした。ゲオルギー・イワーノヴィチの平たい尻が、開いてある見本刷りの上に覆いかぶさっていた。〈中略〉ゲオルギー・イワーノヴィチは屁を放った。毛の生えていない彼の尻がぶるんと揺れた。肉づきの悪い二つの尻の間から褐色のものが現れ、みるみる大きく長くなっていった。〈中略〉ソーセージが途切れて、彼の両手に落ちた。つづいて、先よりもやや細めで、色も薄めの二本目が出てきた。フォーミンはまたそれを両手で受けた。ゲオルギー・イワーノヴィチの短くて白いペニスが揺れたかと思うと、黄色い液体が勢いよくほとばしり…」ソローキン著 亀山訳 『新装版 愛』, 2023, p. 211-212
本書の巻末には著者ソローキンのインタビューや訳者である亀山郁夫さんのソローキン論があるので、文学史上のソローキンの立ち位置などはそちらを参照してほしい。
本書を…いやソローキンを読んで思うのは、ソローキン文学で目立つ死体愛好、同性性交やスカトロジーは人間の深層的かつ根本的願望であると知らされることだ。
「いやいや、ふつうの人間はそんなことおもわないぜ!」と思っているあなた。ほんとうにそう言い切れますか?
子どもの頃に「うんこ」「おしっこ」を面白がっていませんでしたか? 恋人や伴侶の糞尿をなめてみたことはないのですか?
性に目覚めたころに自分の性器をいじったり、手鏡を使って見えない部分を見たり、においをかいだりしませんでしたか? セックスに満ち足りていたとしてもオナニーはしないのですか?
祖父母や家族の死体に何かしらの興味を持ったりしたことはありませんか? 街で事故死体や行き倒れがいたら好奇心で見に行きませんか?
社会という共同幻想の中に入るこによって、他人には秘匿しなければ村八分にされると不謹慎のくくりに入れ、心の中にしまっているだけではありませんか?
この『愛』にある一般的不道徳性は私にとって、読み進めるうちに喜びとなっていたことを正直に打ち明けたい。ソローキンはすべての人間が承認欲求を所有しているのとおなじように、「エロス」と「タナトス」をすべての人間が根本的に持っていると確信をし、深層心理からそれを呼び起こす高度な技法をもって読者にそれらを提示をする。
(国書刊行会 2023年 初版第1刷)